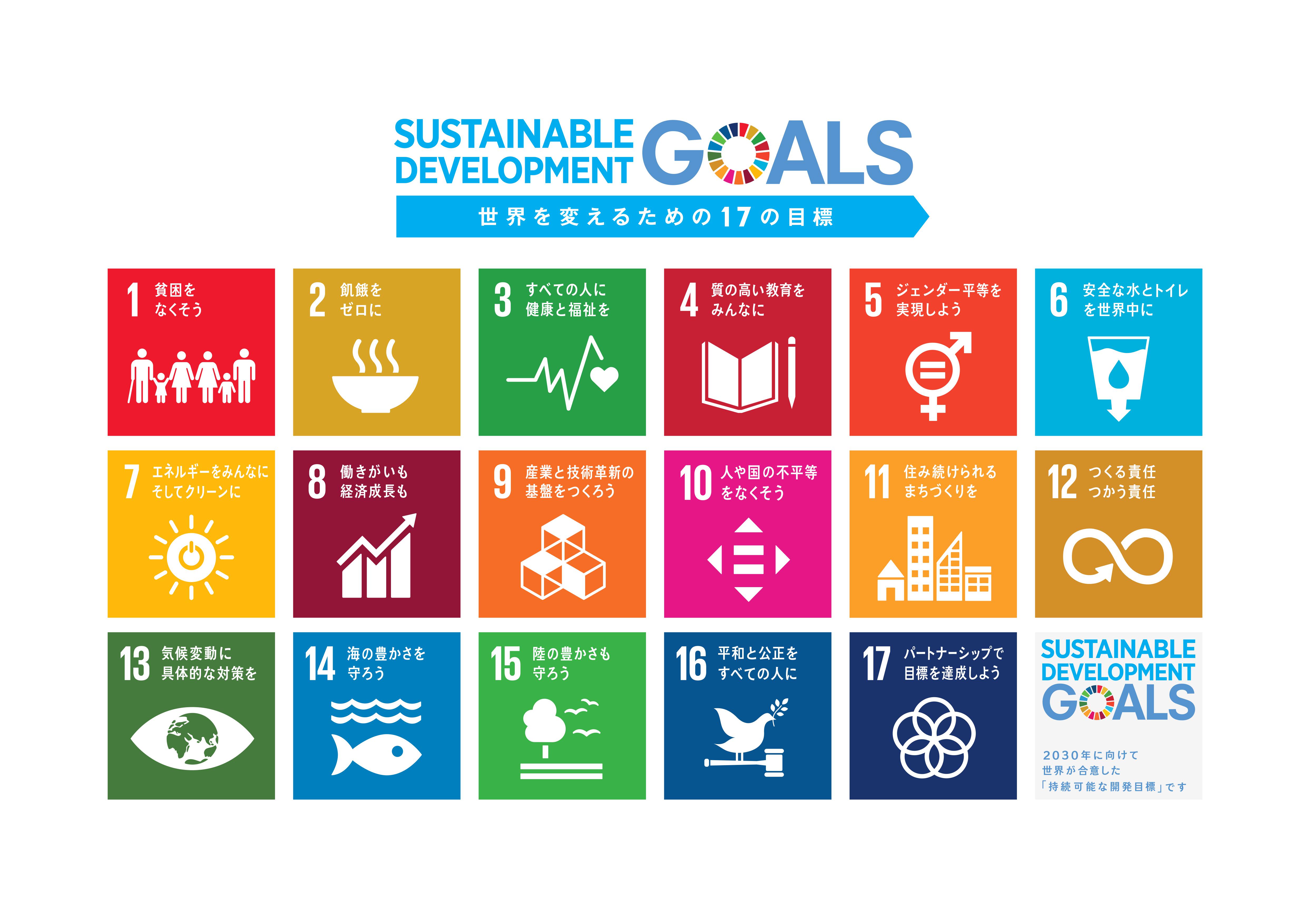
国内金融大手5社が「脱・脱炭素」したので国内繊維産業にも影響がありそうだという話
2025年4月3日 トレンド 0
繊研新聞に掲載されたこの記事は興味深かった。
米国、仏企業に反DEI通達 ラグジュアリーなど幅広い業種が対象に | 繊研新聞
在仏米国大使館が、DEI(多様性・公平性・包括性)に関連する方針の撤回を求める書簡を仏企業に送付していたことが明らかになった。仏の経済紙が報じたもので、対象は米政府と契約関係を持つ通信、エネルギー、製薬、ラグジュアリーなどの企業や法律事務所。
この書簡では、DEIを推進していないことを証明する書類の提出が求められており、背景には23年に米最高裁が「人種などを考慮した大学入試の優遇措置」(アファーマティブ・アクション)を違憲と判断したことと、トランプ大統領が掲げる反DEI方針があるとされる。
とのことで、さらに
また英国の報道では、同様の書簡が東欧諸国を含むEU(欧州連合)域内の複数の大企業にも送付されていると報じている。対象はいずれも米政府との契約関係を持つ企業という。
と続く。
個人的にはこの通知は早晩日本にも来るだろうと見ている。
基本的には多様性には賛成だが、2010年代以降の急進的ともいえる動きには反対であるから、今回のアメリカ政府の動きも理解できる。
これと同様のことが「脱炭素」で先行して起きていたことは以前にもこのブログで書いた。
その続報だが、現状はこのようになっている。
みずほも脱炭素目指す金融機関枠組み離脱 残るは三井住友トラストグループのみに(テレビ朝日系(ANN)) – Yahoo!ニュース
地球温暖化に懐疑的な第2次トランプ政権が誕生して以降、ゴールドマンサックスなど世界的な金融機関の離脱が相次いでいて、日本でもすでに三井住友フィナンシャルグループや野村ホールディングス、三菱UFJフィナンシャルグループ、農林中央金庫が離脱しています。
みずほフィナンシャルグループの離脱により、参加を続けている日本の金融機関は三井住友信託銀行を傘下に持つ三井住友トラストグループのみとなりました。
とのことで、野村HDが脱退した報道は知っていたが、その後、三井住友トラスト以外の三行も離脱したことはこの報道が出るまで知らなかった。
この枠組みに参加していた我が国のメガバンクは全部で六行だったから、5つが脱退してしまったということになる。三井住友トラストGだけが残っているが、これが離脱するのも時間の問題ではないかと個人的に予想している。
先に金融の「脱・脱炭素」について書いたときに、他国の金融が追随する理由について「米国政府や政府に追随する企業との契約がある場合、歩調を合せることが求められる」ことを挙げたが、今回報道された「脱・DEI」でも同様のことが起きたわけである。
しかし我が国の繊維・衣料品業界を見渡した場合、DEIに関しては欧米ほどには急進的ではなかったから、あまり影響は受けにくいと考えられる。
一方、「脱・脱炭素」についてはかなりの影響が今後は出てくるのではないかと考えられる。
我が国の衣料品国内市場も市場で展開するブランド数もすでに飽和状態にあると感じられる。そのため、越境ECを始めとして消費意欲の旺盛な米国市場へ参入しようとする動きが強まっている。そして、かつての欧米に追随する形で「脱炭素」を謳っている商材や素材が多い。
それは2025年以前の欧米の姿勢を見ると、必要不可欠なことだったのだが、2025年以降は特にアメリカ向け商材・素材では行き過ぎた脱炭素は難しくなると考えた方が良いだろう。
欧州は今回のアメリカ政府の動きには抵抗する気配を見せているから、脱炭素を謳った商材や素材は欧州向けとしては引き続き受け入れられやすいだろう。
しかし、欧州の金融も「脱・脱炭素」し始めていると言われている。
欧州の金融でも「脱・脱炭素」が主流になった場合は、欧州向けの脱炭素商材・素材の輸出もムードも鈍化することになると考えられる。
政府の通達や法律や条例の施行は、翌日からすぐに影響が出ることは少ないが、三カ月後とか半年後くらいから影響が出始めることが多い。
今回の「脱DEI」はさておき、「脱・脱炭素」の動きはより顕著に我が国の産業分野に影響を及ぼし始めることになるだろう。
今後も脱炭素の技術開発は続いていくことにはなるし、今回離脱したみずほFGも融資を言明しているものの、2024年までのように「脱炭素」が最優先されるというムードではなくなるだろう。
もちろん、国内市場だけで製造・販売する分においては米国政府の影響はほとんど無いだろうから、脱炭素商材でもDEI商材でもこれまで通りに製造・販売することは可能である。
ただし、グローバル企業、特にアメリカ市場を重点的に開拓している場合はかなりの影響を受けざるを得ないので、その辺りの対応が必要不可欠になるだろう。
2024年までとは異なる世界が始まったわけだが、このムーブメントが短命で終わる可能性もあるが、逆に定着する可能性もある。当方の活動はグローバルなんて関係ないが、グローバル展開をしている企業やそれを目指している企業は難しい舵取りが迫られることになる。








